「森にかよう道」 -知床から屋久島まで- 内山 節著 新潮選書
ここ数年、以前入手した本を読み直すことが多くなりました。年齢と共に本の読み方も、自分自身も変わっているので、読み直しも新鮮な読書経験ではあります。
この本もそんな本のひとつです。平易に語られていますが内容は難しい課題ばかりです。ずーっと気になっている本ですが私には未消化のままの本なのです。
自然保護を訴えるリポートではありません。日本全国を旅してそれぞれの人たちが自然や森とどのように係わり、過去にどのように係ってきたのか、そしてこれからどのように係るのが望ましいのかを探る旅だと思います。
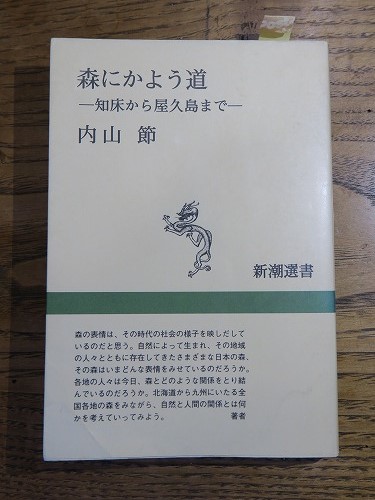
戦後のわが国は山村は人口流出が続いて過疎化が加速しています。なぜかと考えて見ます。いろいろな理由はあるでしょう。豊かであれば人はそこに留まるでしょう。二次産業が生み出す富に、一次産業が飲み込まれてしまったのでしょうか。森が生み出す富は早くても四・五十年かかります。そもそもこの時間が人間と森に代表される自然と係るキーワードではないかと著者は繰り返し述べています。
著者は哲学者です。物事の原点に立って物を見るといったらいいでしょうか。
数百年を単位とする森の時間と、一年一年のサイクルで生活し、7・80年の時間で暮らす人間とどのように調和を取ればいいのか。いい換えれば森の時間はほとんど変化しない悠久の時間であることに対して、人間の生は短い中におどろくほど価値観の変動する時間を有することです。このギャップは簡単に乗り越えることはできません。人間の生の本質に係ることだからです。近代化に伴って私たちは生産のつもりであったものが破壊であったりするのです。もっと大きく見ればひとつの文明が滅亡するという失敗を人間は何度も繰り返してきているのです。その中から人間は何を学んできたのでしょうか。何一つ学んでいないのかとも思えます。歴史から学ぶとは、言葉の上だけのことなのでしょうか。余りにも重く困難な課題です。
自然を経済的な資源とする現代社会。この価値は時代と共にめまぐるしく変動します。現に戦中、戦後に植林された針葉樹林は目を覆いたくなる惨状です。一方、森では悠久と言っていい時間が流れているのです。この森の時間を強引に人間と同じ時間軸に変えてしまおうという試みが現代社会の一部にあるのではないでしょうか。
もっとゆっくりとした時間軸で森を大きく変えず、少しづつ必要なものを利用させてもらうという仕組みを作ってゆくことは可能ではないのか。そういう試みもなされつつあるようです。
ヨーロッパでは、ひとつの具体的な方法で自然を保全する工夫をしています。
西欧の農村風景は絵のような、昔からの落ち着いたたたずまいを見せて、日本からの旅行者を魅了しているようです。古い風景画と同じ景色が今に残っていることも稀ではないようです。この風景を維持している根拠は筆者は次のように述べています。
『人口は国土に適正に配分され、各地域の暮らしが維持されていることが国民全体の利益につながる』という、昔からのヨーロッパの人々の考え方があった。国をあげて山村を維持していこうという政策がなかったら、都市と農村の暮らしが対等の価値として認められる精神風土は生まれることはなかったであろう。という。農村の「条件不利地域」「環境鋭敏地域」といわれる地域で農地の傾斜度、広さ(狭さ)、土壌条件、気象条件、農業基盤(水路、道路など)を、改良、改変、近代化してゆくのではなく。農業の生産性を低下させてでも環境維持をはかるほうが好ましく、そのための農家の損失に対し国が所得を保証し、環境と地域社会の維持を同時に実現しようという政策を生んだ。日本のように市場経済に任せておいたら、環境は守れない。
環境という公的な価値を守るためには公的な政策が必要であり、環境を守る農業を推進するには、農業の近代化はプラスにならず、伝統的な農業を守りながら山村を維持するほうが、そこを訪れる都市の人々にとっても、国民の利益にもなる。というのだ。何と明快な政策ではないか。このような政策によって農村の人々は誇りを持って農村で暮らしを続けることができる、というのだ。
紹介した本のほんの一部にしか触れなかったが、長くなるのでこの辺で。
